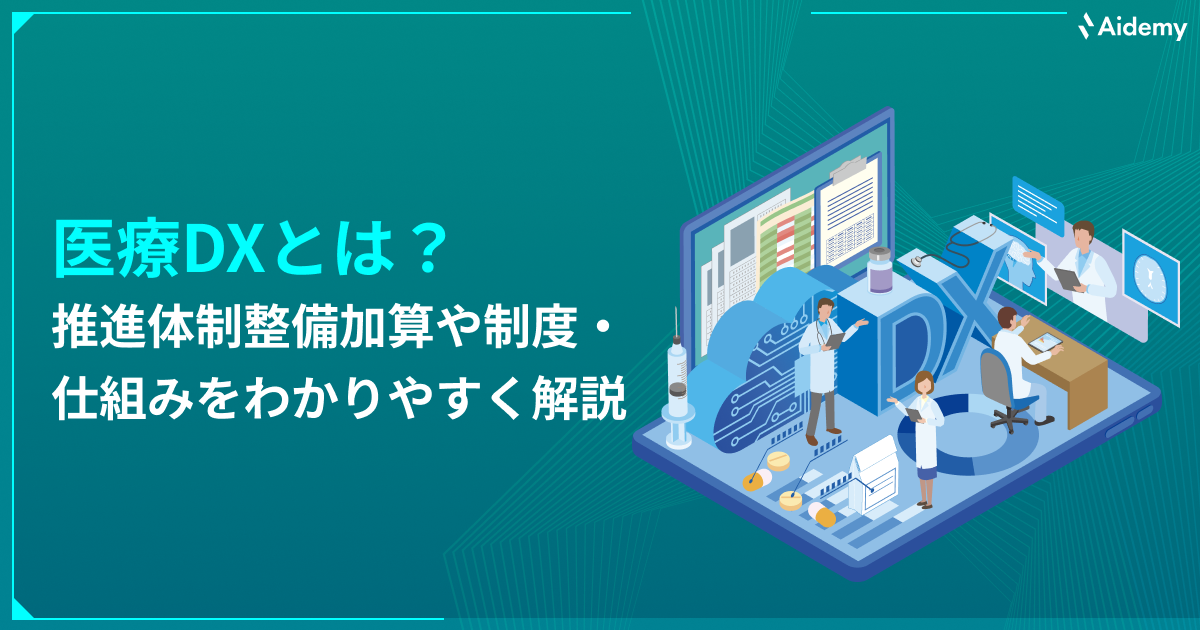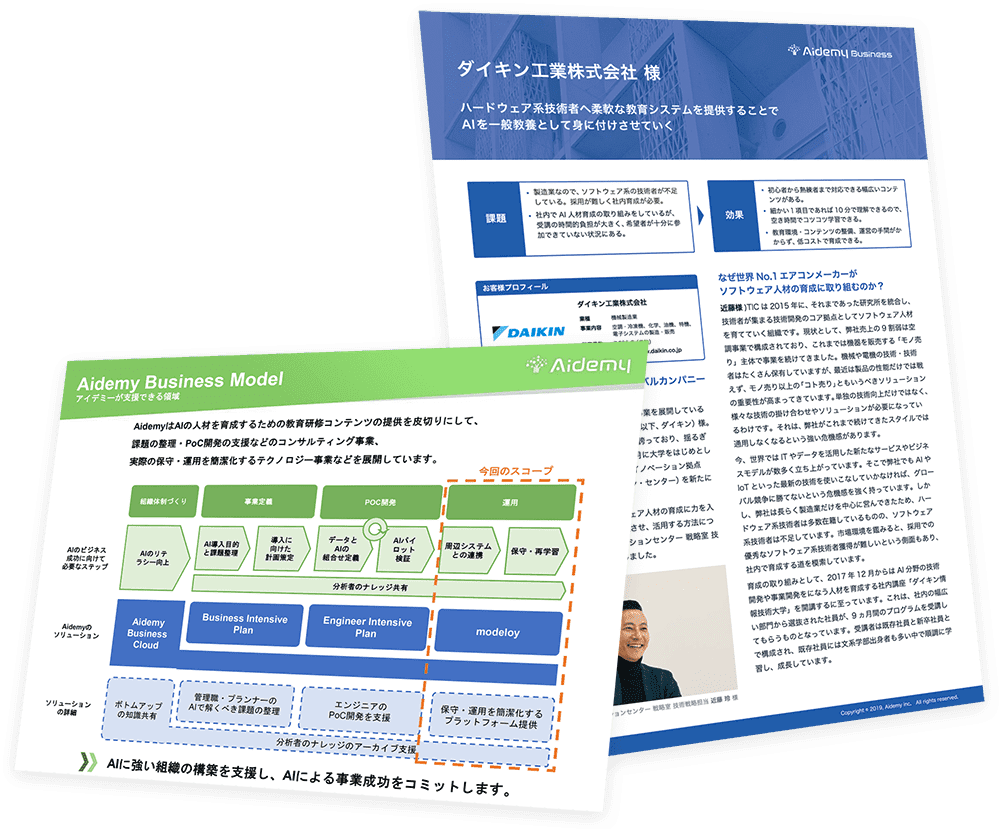医療DXは、診療情報・薬剤情報・請求業務をデジタルで統合し、患者安全と業務効率を同時に高める国家プロジェクトです。全国医療情報プラットフォーム、標準型電子カルテ、診療報酬改定DXという三本柱を軸に、保健・医療・介護を横断して進むデジタルトランスフォーメーション(DX)による再構築の全体像をわかりやすく解説します。
※本内容は2025年8月時点の内容となっております。
目次
医療DXとは?(読み方・定義・背景)
医療DXとは、「診療情報をつなぐ」「薬剤情報を活用する」「請求・改定対応を賢くする」という三本柱で、患者安全と業務効率を同時に高める国家的な取組みです。本章では、医療DXの定義や背景をわかりやすく解説します。
医療DXの定義と対象(保健・医療・介護を横断)
厚生労働省は、医療DXを「医療分野でのデジタル・トランスフォーメーションを通じてサービスの効率化や質の向上を実現し、我が国の医療の将来を切り開く取組」と位置づけています。
医療DXでは、以下の5つのゴールが示され、これらを保健・医療・介護の横断で進めていくのが特徴です。
なぜ医療DXが必要なのか?
- 国民の健康増進
- 切れ目ない質の高い医療の効率的提供
- 医療機関等の業務効率化
- システム・人材の有効活用
- 医療情報の二次利用の環境整備
日本は急速な高齢化と人口減少に直面し、医療需要の質・量の変化、医療従事者の負担増、財政の持続可能性といった課題が同時多発しています。データに基づく標準化・省力化・連携強化なしに現場だけで解決するのは困難です。
そこで、政府は工程表に基づき、共通基盤の整備と標準化に舵を切りました。以下は、医療DXの推進に関する工程表の全体像です。
医療DXの三本柱は?
医療DXの三本柱は、以下の3つです。
① 全国医療情報プラットフォーム(オンライン資格確認の拡張・救急時閲覧 等)
② 電子カルテ情報の標準化・標準型電子カルテ・電子カルテ情報共有サービス
- ③ 診療報酬改定DX(共通算定マスタ/共通算定モジュール・電子点数表)
それぞれ詳しく解説します。
① 全国医療情報プラットフォーム(オンライン資格確認の拡張・救急時閲覧 等)
国はオンライン資格確認等システムを核に、「全国医療情報プラットフォーム」へ拡張します。救急で患者の同意取得が難しい場面でも、適正な手順の下で必要な医療情報を参照できる救急時閲覧の仕組みが順次整備され、災害や広域搬送時にも切れ目ない診療を支えます。
出典:厚生労働省[全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)]
プラットフォームは、患者利便と医療安全、そして現場の業務効率化の両立が狙いです。
② 電子カルテ情報の標準化・標準型電子カルテ・電子カルテ情報共有サービス
2030年には、「概ねすべての医療機関で、必要な患者情報を共有できる電子カルテ」の普及を目指していますが、その実現に向けて、以下が順に進められる予定です。
- 既存システムの標準化(ベンダー間・施設間で情報が連携できるようコードや様式を整備)、
- 未導入向けの「標準型電子カルテ」(国主導のSaaS型。標準APIやデータ移行の互換性等を備える)、
- 電子カルテ情報共有サービス(医療機関間で必要な情報を共有する中核サービス)
以下は、標準型電子カルテの意義と特徴です。
出典:厚生労働省[第3回標準型電子カルテ検討ワーキンググループ資料]
2024年度に標準型電子カルテのα版が開発・試行され、2026年度に完成目途、各種要件・支援策と合わせて普及が図られます。オンプレからクラウド・ネイティブへの移行設計も、費用対効果とセキュリティの両面から推奨されています。
厚生労働省の電子カルテ情報共有サービスも参考になりますので、ご確認ください。
③ 診療報酬改定DX(共通算定マスタ/共通算定モジュール・電子点数表)
「診療報酬改定DX」は、医事・レセの作業負担と改修コストを構造的に下げる取り組みです。国が共通算定マスタと共通算定モジュール(将来的にクラウド間連携を基本)を整備し、電子点数表の改善や施行時期の後ろ倒しなどとセットで、ベンダーロックインの緩和と算定・請求の精度向上を狙います。
対象の広がりや時期は段階的に示され、中小病院・診療所にも導入効果が及ぶ設計です。
医療DXの三本柱は「共通基盤 × 標準化 × 運用DX」の関係です。 プラットフォームが“つながる土台”を提供し、標準化された電子カルテ/共有サービスが“データの品質・再利用性”を担保し、診療報酬改定DXが“日々の業務と収益管理”を合理化します。
この整合設計により、単発導入では得られないスケールメリット(安全性の底上げ、人的負荷の平準化、投資回収の見通し)を確保できます。経営としては、更改サイクル(5–7年)に合わせたクラウド移行と、加算・補助を活用した分割投資が合理的です。
医療DXのロードマップ(2025→2030)
医療DXは、単なるデジタル化ではなく、医療現場の仕組みそのものを進化させる国家プロジェクトです。この章では、2025年から2030年にかけて進む電子カルテの標準化や共有サービス、介護情報基盤の整備スケジュールを整理します。
今後の経営判断や現場対応を考えるうえで、押さえておきたい重要なポイントを時系列で確認していきましょう。
【2025年】「つながる基盤」を現場で動かし始める年
2025年(令和7年)は、医療DXの要となるプロダクトや制度が実地で動き始める節目の年です。標準型電子カルテのα版が無床診療所でモデル導入され、電子カルテ情報共有サービスも一部医療機関でモデル事業として運用が進みます。
電子カルテの普及率は、医科診療所:約55%、一般病院:約65%(2023年医療施設調査)
電子カルテ未導入の医科無床診療所向けに、国がクラウドベースの標準型電子カルテを開発中。本年3月末より、一部医療機関でモデル事業を実施。
電子カルテ情報共有サービス(以下「共有サービス」)については、本年2月より、一部医療機関でモデル事業を実施。本格運用に必要な法制上の措置を規定した「医療法等の一部を改正する法律案」を第217回通常国会に提出
引用元:厚生労働省|電子処方箋・電子カルテの目標設定等について
さらに、電子処方箋は薬局での運用が全国的に一般化(2025年6月時点で導入8割超、夏には概ね全店導入見込み)し、医療安全(重複投薬・併用禁忌の回避)に資するエコシステムが整備段階に入ります。
加えて、スマートフォンでのマイナ保険証の実証が7月から始まり、9月頃をめどに読み取り端末普及を含めて利用環境の整備が図られます。これらは全国医療情報プラットフォームの拡張に直結する動きです。引用元:[デジタル庁|平デジタル大臣・福岡厚生労働大臣が、スマートフォンをマイナ保険証として利用可能とする実証事業を視察しました]
【2026年】標準型電子カルテの完成目途と普及計画の明確化
2026年(令和8年度)には、標準型電子カルテの完成を目途に、医科診療所向けの標準仕様(基本要件)策定、政府クラウド対応、標準API、互換性確保(データ引継ぎ)といった導入要件が具体化します。
医療機関側の普及計画は「2026年の夏までに取りまとめ」とされ、オンプレ中心の病院についても次回更改時にクラウドネイティブへ移行する方向性が明示されています(医療情報化支援基金の活用や段階的アップデートを想定)。
出典:[厚生労働省|電子処方箋・電子カルテの目標設定等について]
電子処方箋は、「患者情報を共有する電子カルテを整備するすべての医療機関」へ導入する新目標のもと、電子カルテ/共有サービスとの一体導入が基本方針になります。
医薬品コード(YJ・レセ電・一般名)や臨床検査コード(JLAC11)の整備も工程に含まれ、2026年度から関係性を国が明らかにする取り組みが始まります(ダミーコード排除などシステム安全性の強化)。導入設計時にマスタ運用の更新計画をあらかじめ織り込むと移行がスムーズです。
【2030年】「概ねすべての医療機関」で共有可能な電子カルテへ
国は「遅くとも2030年には概ねすべての医療機関で、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテを導入」という目標を掲げています。これは、個々の施設最適から地域・全国の最適へ軸足を移すことを意味し、救急・災害・広域搬送・慢性疾患の継続ケアにおける情報連携の確度を大きく引き上げます。
医療法人を運営しているのであれば、ベンダー選定(標準仕様準拠)→クラウド移行→共有サービス接続→運用高度化(算定DX/データ活用)のロードマップを逆算で設計するのが合理的です。
【2028年】介護情報基盤—2028年度本格運用へ、医療連携が現実解に
介護情報基盤は、2028年度(令和10年度)本格運用開始を目指し、市町村システムの標準化・データ移行を前提に順次2026年度から連携開始のスケジュール感です。
主治医意見書、入退院時の情報連携、在宅・施設ケアのデータ往来が電子化されることで、退院支援・地域包括ケアの運用が軽量化します。
病院・診療所としては、地域連携パスのデジタル化や多職種連携プロトコルを整備しておくと、介護基盤の本格稼働と同時に効果が出やすくなります。
医療DXの電子処方箋(現状・新目標・効果)
電子処方箋は、医療DXの中でも特に現場の安全性や業務効率に直結する重要な仕組みです。薬局ではすでに導入が進んでいますが、医療機関での普及はまだこれから。今後は電子カルテや情報共有サービスと連動した形での本格展開が求められます。
この章では、現在の導入状況と新たに掲げられた目標、そして電子処方箋がもたらす具体的な効果について、経営判断に役立つ視点で整理します。
2025年夏時点の普及状況(薬局はほぼ導入完了、医療機関は立ち上げ途上)
2025年6月22日現在、オンライン資格確認システム導入施設のうち電子処方箋の運用開始済は33.0%。内訳を見ると、薬局は導入が8割を超え、申請済(運用開始含む)は9割超で、夏頃には概ねすべての薬局で導入と見込まれます。一方、医療機関の導入は約1割(医科19.1%)にとどまっており、今後の普及が課題です。
こうした足元の状況を踏まえ、調剤結果の登録引き上げと医療機関側の導入拡大が今後重要とされています。
薬局側は紙処方箋を含め調剤結果情報の登録(引用元:電子処方箋管理サービス)が進み、2025年5月時点で登録割合は全体の約8割に到達。重複投薬等チェックの実行も増加しています。
新目標—「患者情報を共有する電子カルテ」を整備するすべての医療機関で導入
従来の「2025年3月までに概ね普及」という薬局中心の目標から転換し、電子カルテ/電子カルテ情報共有サービスとの“一体導入”を軸に、「患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備するすべての医療機関」への導入を目指す新目標が示されました。
参考:厚生労働省[電子処方箋・電子カルテの目標設定等について]
医療機関側の導入は電子カルテが前提であり、既導入機関は次回更改(5~7年周期)で共有サービス対応と併せて改修、未導入機関は標準型電子カルテ(SaaS)など標準仕様に準拠したクラウド型の採用を進める方針です。
併せて、2025年8月に電子処方箋管理サービスで「ダミーコードを受け付けない」改修が完了する計画や、医薬品コード(YJ・レセ電・一般名)の関係性の明確化(R8年度~)、臨床検査コードのJLAC11標準化といったマスタ整備が進みます。導入設計の早期段階からコード/マスタ運用の更新計画を組み込むと現場負担を抑えられます。
医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コードの設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態であるかについて厚生労働省へ点検報告を完了した医療機関・薬局のリストを掲載しています。(原則金曜日に更新します。)
引用元:厚生労働省|医療機関・薬局の電子処方箋対応状況について
医療安全・業務効率への効果—“電子処方箋ならでは”の改善ポイント
医療安全:2024年度には、電子処方箋を導入した医療機関・薬局において重複投薬アラートが約3,600万件/年、併用禁忌アラートが約5.1万件/年発生。処方・調剤時のリスク抑制に実績ベースで寄与しています。
災害時・救急時には患者の直近の薬剤情報が確保され、治療の継続性を高めます。
薬局側の調剤結果登録が電子処方箋管理サービスで一元化されることで、相互作用チェックや処方監査の精度が向上し、問い合わせ・差し戻しの減少、待ち時間短縮が期待できます。また、医療機関側も電子カルテ情報共有サービスとの一体運用により、持参薬確認や重複処方回避の効率化が見込めます。
医療DXの標準型電子カルテと情報共有サービス(要件・移行)
電子カルテの導入・更新は、医療機関のIT投資において最も大きな判断のひとつです。医療DXの進展に伴い、今後は標準仕様に準拠したSaaS型電子カルテと、全国医療情報プラットフォームとの接続を前提とした情報共有サービスへの対応が求められます。
この章では、標準型電子カルテの要件や情報共有サービスの制度設計、オンプレミスからの移行方針、導入支援策、そして普及に向けたロードマップについて整理します。
標準型電子カルテの要件(SaaS/標準API/互換性・政府クラウド対応 ほか)
国は小規模医療機関でも過度な負担なく導入できることを前提に、標準型電子カルテの方向性を示しています。中核はSaaS(マルチテナント)型のクラウドサービスで、電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋に対応し、ガバメントクラウド対応、標準APIの搭載、データ引継ぎが可能な互換性などを備えることが要件です。
また、技術面の補足として、FHIR等の準拠仕様、API連携、署名・検証やマスタ(コード)運用の考え方は、「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(案)」にて、ベンダ向け技術資料に整理されています。
電子カルテ情報共有サービスの制度設計(3文書6情報・同意・運用の枠組み)
電子カルテ情報共有サービスは、「全国医療情報プラットフォーム」を構成する中核機能で、他院の電子カルテ情報の一部を、患者の同意に基づき閲覧できる仕組みです。
提供・閲覧対象は、「3文書(健診結果報告書/診療情報提供書/退院時サマリー)」+「6情報(傷病名・感染症・薬剤アレルギー等・その他アレルギー等・検査・処方)」の枠組みで整理され、同意や目的外利用禁止などの運用ルールが示されています。
また、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室が「文書情報(3文書)及び電子カルテ情報(6情報)の取扱について」についてまとめているので、そちらも併せてご確認下さい。
本サービスに対応しているシステムベンダは、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にてご確認いただけます。
なお、救急時医療情報閲覧は別枠の運用で、患者の生命・身体の保護が必要な場合に限り、適正な権限管理・二要素認証・履歴確認の下で参照できる仕組みが段階導入されています。詳しくは、【救急時医療情報閲覧:概要案内】/【救急時医療情報閲覧機能導入に向けた準備作業の手引き】をご確認下さい。
オンプレ→クラウド・ネイティブ移行(更改サイクルと補助の活用)
病院情報システムの高コスト構造(オンプレ+個別カスタマイズ)からの脱却に向け、国は2025年度を目途に病院向け標準仕様(基本要件)を策定し、標準仕様に準拠したクラウド・ネイティブ製品が登場した段階で順次移行する方針を示しています。
次回システム更改(5~7年サイクル)での共有サービス/電子処方箋対応を促し、医療情報化支援基金等の活用で改修を後押しします。
モデル事業(α版)と普及計画(2026年度「完成」目途)
標準型電子カルテのα版は無床診療所でモデル事業として試行が始まっていますが、そこで得られた改善点を取り込みつつ、2026年度中の完成と普及計画(2026年夏までに取りまとめ)が示されています。
医療DXの診療報酬改定DX(コスト低減設計)
医療DXの取り組みを評価する新たな診療報酬加算として、「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が設けられました。
これらは単なる加算ではなく、オンライン資格確認や電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスといった、今後の医療インフラの活用を前提とした体制整備を促すものです。
この章では、それぞれの加算の目的・点数・施設基準に加え、掲示義務や運用上の注意点など、現場での対応に直結する実務ポイントを整理します。
共通算定マスタ/共通算定モジュールの狙いと提供方式
診療報酬改定DXの中心は、算定・請求の“共通部分”を国が標準提供することで、毎回の改定で発生していた大規模改修の負担を恒常的に下げることです。
以下の2点がポイントです。
- 共通算定マスタ:基本マスタの充足化に加え、共通算定マスタ・コードと地単公費マスタを整備。ルールを明確化し、仕様のブレを減らします。
- 共通算定モジュール:診療報酬の算定/患者負担金の計算を実施し、将来的にレセプト作成・請求支援まで射程に。クラウド型レセコンとの“クラウド間連携”を基本とした提供が想定されています。
位置づけとしては、全国医療情報プラットフォームと連携しつつ、医療機関等の負担を極小化するのが最終ゴールです。必要に応じて標準型レセコンの提供も検討に含まれます。
施行時期の後ろ倒し・電子点数表の改善による改修コスト低減
「改定のたびに短期間で大型改修」になると大変です。この作業ピークを避けるために、次のような手当てが同時に走ります。
- 改定の施行時期を“後ろ倒し”して、開発・テストの時間的余裕を確保
- 点数表ルールの明確化・簡素化で仕様解釈のばらつきを抑制
- 電子点数表の機械可読化/更新容易化で、反復作業の負荷を軽減
この組み合わせにより、ベンダー側の改修負担も院内運用(医事・会計)側の手戻りも平準化できます。
標準型レセコン標準仕様(2025年度目途)とロックイン緩和
標準型レセコン標準仕様は、国が策定(2025年度目途)し、準拠製品は民間が開発します。この役割分担は、ベンダロックインを緩和し、市場原理でコストを引き下げていく考え方です。
加えて、レセプト請求に係るコア共通機能は一元的に開発して各社が活用するため、重複開発のムダを抑えられます。なお、オンプレミス型レセコンについては、当面はオンプレ向けモジュール提供から対応を開始します。
導入スケジュール(中小病院→診療所へ拡大、令和8年度から本格提供)
導入は中小規模病院から段階的に開始し、令和8年度(2026年度)以降は、クラウド間連携を基本として既にクラウド型レセコンを使う医科診療所などへ提供を広げます。
導入の実務は、新設・更改のタイミングに合わせて進め、費用対効果に応じた加速策も講じられます。前章で述べた標準型電子カルテ/電子カルテ情報共有サービス、コード・マスタ整備とも歩調を合わせ、全体最適を図る工程です。
医療DXの推進体制整備加算・医療情報取得加算(実務)
医療DXを具体的に進めるうえで避けて通れないのが、診療報酬に関する制度対応です。
2024年度の診療報酬改定では、「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が新設・再設計され、オンライン資格確認や電子処方箋の活用体制が評価対象となりました。
この章では、加算の点数や施設基準だけでなく、掲示義務や運用上の注意点まで、医療機関として対応すべき実務ポイントをまとめています。
医療DX推進体制整備加算の目的・点数・施設基準(経過措置・利用率要件を含む)
出典:厚生労働省保険局医療課[令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】]
医療DX推進体制整備加算は、診察室等でオンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用し、加えて電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスを整備するなど、医療DXの中核体制を評価する新設加算です。
医療DX推進体制整備加算は、医療の質向上、業務効率化、患者サービスの向上を目的としています。
医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直しについては、下記の図が参考になります。
参考:厚生労働省保険局医療課[医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて]
医療情報取得加算の点数・頻度・掲示義務
医療情報取得加算は、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を再設計し、オンライン資格確認を通じて得た診療情報を実際に取得・活用した診療を評価する仕組みです。
参考:厚生労働省保険局医療課[令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】]
点数・頻度(医科・歯科共通の基本像)
- 初診:医療情報取得加算1(3点)/同2(1点)
- 再診:医療情報取得加算3(2点)/同4(1点)(3か月に1回に限り算定)
施設基準(要旨)
- 電子請求、オンライン資格確認体制。
- オンライン資格確認の実施と診療情報の活用(受診歴・薬剤情報・特定健診等)。
- 院内掲示+Web掲示(体制と活用方針の明示)。
詳しくは、前述した「医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し」をご確認下さい。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについては、別資料が参考になります。
医療DXのメリットとは?(KPIと優先順位)
医療DXは現場の利便性を高めるだけでなく、経営的にも多くのメリットをもたらします。診療の安全性や業務効率の向上にとどまらず、災害対応力や地域連携、さらには収益性やデータ活用の高度化にもつながっていきます。
この章では、医療DXがどのような指標(KPI)で効果を可視化できるのか、そして限られたリソースの中で何から優先すべきかを整理します。
患者安全の向上(重複投薬・併用禁忌の回避、災害・救急での継続性)
医療DXの導入は、最初に安全性の底上げから実感できます。電子処方箋の普及に伴い、2024年度には重複投薬アラート約3,600万件/年、併用禁忌アラート約5.1万件/年が確認され、処方・調剤時のリスク抑制に寄与しています。また、薬局側の調剤結果登録割合が約8割に到達し(2025年5月時点の推計)、直近の薬剤情報を基に安全性を確保する運用が進んでいます。
さらに、救急時医療情報閲覧により、患者の生命・身体の保護が必要な場面では適切な手順の下で同意取得が困難でも必要情報にアクセスでき、治療継続の確度を高めます。
以下は、安全性に関するKPI例です。
- 重複投薬/併用禁忌アラート対応率(例:対応完了/要精査/見送り)
- 調剤結果登録率(自院患者の処方に紐づく登録の捕捉率)
- 電子処方箋発行率(診療科・外来種別別)
- 救急時閲覧の適正利用率(権限・二要素認証・監査の充足)
生産性・業務効率の改善(紙業務削減、待ち時間短縮、請求精度)
診療報酬改定DXは、共通算定マスタ/共通算定モジュールの提供や電子点数表の改善、改定施行時期の後ろ倒しなどで、改修作業の山を平準化しつつ請求精度の底上げを狙います。
これにより、返戻・再請求の低減、教育・周知に要する手間の縮小が見込めます。
また、電子カルテ情報共有サービス(標準化・API連携)と標準型電子カルテ(SaaS)の組み合わせは、持参薬・既往歴の確認工数削減や処方監査の質向上、院内の情報共有コスト低下に直結します。
以下は、生産性に関するKPI例です。
- 平均待ち時間(受付→診察/診察→会計)
- 紙様式→電子様式の移行率(計画書・同意書・紹介状 等)
- 返戻率/再請求率(診療科別・月次)
- 職員1人当たり処理件数(医事・薬剤・看護の主要業務)
BCP/災害・救急対応力の強化(救急時医療情報閲覧の活用)
救急時医療情報閲覧は、一次~三次救急の受け入れ病院を中心に段階導入が進み、二要素認証・閲覧履歴確認などの統制下で、災害・搬送時の情報空白を埋めます。直近の薬剤情報にアクセスできることで、慢性疾患の継続治療や禁忌回避の判断が迅速化します。
経営面でも、治療のやり直しコストの回避や地域での役割発揮(救急・広域搬送)に資するため、優先度の高い内容です。
以下は、BCP(医療施設の災害対応のための事業継続計画)に関するのKPI例です。
- 救急時閲覧の訓練回数/年・平均応答時間
- 災害訓練時の情報取得成功率(閲覧権限・回線冗長性・代替手順)
- 監査ログレビューの実施率(四半期)
データ利活用と経営KPI(収益・品質・連携の見える化)
全国医療情報プラットフォームと電子カルテ情報共有サービス、診療報酬改定DXが整うと、データの品質・一貫性が高まり、KPI経営に直結します。
- 収益:加算の算定率、加算あたり回収額、補助・基金の活用率
- 品質:安全アラート未対応ゼロ、再入院率、周術期合併症率(該当科)
- 連携:紹介受入率/逆紹介率、地域包括ケア連携件数、在宅移行までの日数
- 人材:ITトレーニング受講率、手順書遵守率、権限・ID棚卸完了率
また、標準コード(医薬品コード、検査コードJLAC11等)整備が進むことで、施設横断の比較や二次利用の精度が向上します。
医療DX導入の流れ
医療DXの導入は、単なるシステム更新ではなく、現場の業務フローや経営指標にも影響します。そのためには、段階ごとの取り組みを明確にし、目的に応じた進め方を計画的に実施していくことが重要です。
この章では、初期の現状整理から本番運用、さらに加算の安定化や地域連携の拡張まで、導入プロセス全体の流れを体系的に解説します。
補足として、電子処方箋の体制整備における経過措置は、医療DX推進体制整備加算を算定する医療機関や薬局が、2025年3月31日までに電子処方箋発行の体制を整備するまでの間、体制を整えなくても加算を算定できるというものです。この期間終了後は加算の算定要件を満たさなくなりますが、電子カルテ情報共有サービスに対応するための体制整備は2025年9月末までが経過措置期間とされています。(令和7年8月4日時点 記事執筆時点の情報)
0–3か月|現状棚卸し・要件定義・方針決定
やること(現場ヒアリング+データ確認)
- オンライン資格確認の運用実態(受付・診察室での閲覧フロー、同意取得、監査ログ)[資料1 p.8–11]
- 電子処方箋の発行率/調剤結果登録の捕捉(自院→薬局→管理サービスへの登録の“抜け”を見える化)[資料1 p.5–6]
- 電子カルテの現況(オンプレ/クラウド、次回更改時期、アドオン/連携の一覧)→共有サービス対応の可否[資料2 p.6–8]
- 救急時医療情報閲覧の対象/権限/二要素認証の実装と訓練頻度[資料1 p.10–11]
- 診療報酬改定DXの対応状況(レセコン種別、共通算定モジュール受け入れ可否、返戻率の現状)[資料1 p.12–13]
- 看護・薬剤・医事・情報の業務プロセス(紙様式の残存、API連携のニーズ)
アウトプット
- To-Be要件(標準API、ガバメントクラウド対応、互換性、監査・権限、SLA)[資料2 p.1–2, 6–8]
- KPI初期セット(待ち時間、返戻率、アラート対応率、調剤結果登録率、DX加算算定率)
- 移行方針(当面アップデートで準拠→更改でクラウド・ネイティブ/新規に標準型電子カルテ)[資料2 p.6–8]
3–6か月|RFP作成・ベンダー選定・PoC(小規模検証)
RFPの骨子
- 機能要件:電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス・救急時閲覧・共通算定モジュール接続、標準コード(医薬品/JLAC11)運用[資料1 p.12–13/資料2 p.2]
- 非機能要件:SLA/可用性、監査ログ、ID・権限設計、バックアップ/DR、ベンダロックイン回避(標準仕様準拠)[資料1 p.13/資料2 p.6–8]
- 導入・教育:ロール別トレーニング(医事・薬剤・看護・情報)、経過措置期日厳守の移行計画
PoCの目的と合否条件
- 既存カルテ/レセとのAPI疎通、処方監査・相互作用チェックの実効、診察室での参照性(クリック数・所要時間)
- 返戻率・未対応アラート・待ち時間などKPIの前後差を測定
6–12か月|段階導入・本番切替・定着化(教育・監査)
段階導入(例)
- 外来(特定科)→外来全体
- 処方・調剤連携(電子処方箋“発行”と調剤結果登録の両輪)
- 救急・入院部門(救急時閲覧の定着化、サマリー共有)
- レセ運用(共通算定モジュール接続、電子点数表の更新手順の定常化)[資料1 p.12–13]
教育・定着
- 週次のショートトレーニング+画面ヒント集の配布
- 監査ログの月次レビュー(アクセス権限の逸脱、救急時閲覧の適正性)[資料1 p.10–11]
- 掲示・Web掲示の整合(DX推進体制整備加算/医療情報取得加算の掲示義務)[資料A p.2–5]
本番受入の判定
- KPI(返戻率↓/待ち時間↓/アラート対応率↑/加算算定率↑)が目標レンジに収束
- 経過措置期日までに体制整備の証跡(手順書・教育・ログ)が揃っている
12か月以降|最適化・加算運用の安定化・地域連携の拡張
- KPIの目標引き上げ(科別・時間帯別のボトルネックに対処)
- DX加算の安定算定(マイナ保険証利用率のモニタリング、院内プロモーション)[資料B p.5–6]
- 地域連携:紹介・逆紹介のKPI化、介護情報基盤との接続準備、多職種プロトコルの運用確立[資料1 p.14–15(介護基盤の工程)]
- コード/マスタ運用の高度化(医薬品コード関係の整備、JLAC11移行)[資料2 p.2]
プロジェクト体制(PMO)とリスク管理の勘所
体制(RACI例)
- エグゼクティブスポンサー(理事長/院長):意思決定・資源配分
- PMO(事務長+情報部):計画・進捗・課題・品質・対外調整
- 業務オーナー(医事/薬剤/看護/救急):業務要件と受入判定
- セキュリティ責任者:監査ログ・権限・教育・事故対応手順
主要リスクと対策
- 更改期日遅延:段階導入で“先に満たす”領域を確保/暫定運用手順の合意
- ベンダ依存:標準仕様準拠・API・データ移行の互換性を契約条件に[資料1 p.13/資料2 p.6–8]
- 利用率未達(DX加算):待合・Web・会計での周知導線/スタッフ説明カード
- 監査対応:掲示・手順書・教育記録・アクセスログを四半期で棚卸し
参考
- 資料1:令和7年7月1日 厚生労働省 医療DXの進捗状況について
- 資料2:令和7年7月1日 厚生労働省 電子処方箋・電子カルテの目標設定等について
- 資料A:厚生労働省保険局医療課|令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】
- 資料B:厚生労働省保険局医療課|医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて
医療DXのまとめ!体制整備と人材育成はセットで進めよう
医療DXは、制度対応だけでなく、業務効率の改善や患者満足度の向上にもつながる重要な取り組みです。
その実現のためには、医療機関・法人全体での継続的な体制整備と人材育成が欠かせません。
とはいえ、「何から始めればいいかわからない」「職種別に適切な研修ができない」といった声も多く聞かれます。
そうした課題を解決したい方には、Aidemy Business(アイデミー ビジネス)の導入をおすすめします。
Aidemy Businessは、生成AIやPythonなどを活用したDX人材の育成支援に特化したオンライン学習プラットフォームです。
国の指針である「デジタルスキル標準」に準拠した豊富な研修コンテンツと、人材要件定義・アセスメント・学習促進の一気通貫支援により、多くの企業がDXを加速させています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
また、DX推進に関する他分野の情報もあわせてご覧いただくことで、より広い視野で自組織の方向性を検討できます。
- DX人材とは?スキルマップや必要な資格を事例込みで徹底解説
- DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方
- DX研修でおすすめのeラーニングとは?【事例・感想付き】
- なぜDX内製化が必要なのか?課題や企業の成功例と失敗事例や進め方
- 製造業DXとは?背景や課題・企業の成功事例や取組むメリット
今後の制度改正や技術革新に備え、医療現場にふさわしいDX推進体制を整えていきましょう。